| 「薬売ってるところってここなん?」 尾関倫彦がドアの覗き穴越しに外を見ると傘を携えたポニーテールの少女が立っていた。 深夜に訪れる人間は尾関倫彦にとって珍しくは無かったが小学生くらいの女の子と言うのは始めてだった。倫彦に小学生くらいの少女に対する性的趣味は無かったがそれを補って余る程の可憐な容姿だったのと相手の年齢も考慮して警戒心を薄め てドアを開ける事にした。 「おまえ誰に聞いたんや?」 「友達のお姉ちゃん」 「なるほどね…」 いつも薬物を売りさばいている女子高生または女子中学生の誰かがそうなのだろう。顧客が増える事はいい事だがあまり不用意に言い触らされても困るなと倫彦は思った。 「誰ー?客ー?」 シャワーを浴びた直後の女が出て来た。薬物患者特有のトロンとした目をしている。 (ちょうど、この女にももう飽きてきた所やしな) 「なんか小学生みたいやで」 「うそー、あんた悪人やなあ」 女がケラケラと笑う。そう言うこの女も今年中学を出たばかりだ。倫彦が鍵を開けると少女が中に入って来た。 (ほう。これはこれは) 近ごろの小学生は発育がいいと言うが、その少女はそこら辺りの小娘とは違い、ただ単にむやみに大人っぽくなっていると言うわけでは無く、気品と言うものがあった。髪も漆黒で最近茶髪の女しか相手にしていなかった倫彦には逆に新鮮だった。 トランジスタグラマでは無い。どちらかと言えば中性的な美しさだ。あの細い腰に自分のペニスを突き上げる瞬間を想像し、倫彦はペニスが勃起するのを感じた。 (小学生でもこんなレベルの娘なんか滅多におらんやろな。ま、何事も経験やからな。チッ、この女がおらんかったら。すぐにでも薬飲ませてヤってまうんやけどな) 「で、どんだけ欲しいねん。金は持ってんねんやろな」 「ここに十万。とりあえずはこれだけ。そっちは全部でどんだけあんの?」 少女は万券を十枚ポケットから取り出した。 「最近のガキは金持ちやね」 倫彦は口笛を吹く。しかしまあ珍しいことでもない。 「一応、五十錠入りが一箱で普通はバラ売りや。今んとこ在庫は十ダースくらいかな。もっといるんやったら用意するけど」 交渉する間にも倫彦は少女の身体を舐め回す様に見定める。美少年と言っても通じるかもしれない。倫彦は身体よりもこの整った顔が官能に歪む表情を見てみたいと思い始めていた。もちろんこの薬を使ってだが。 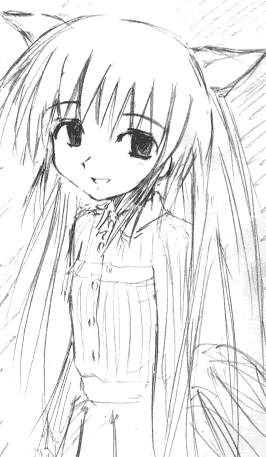 「とりあえず十万やったら四十錠やな。これでもだいぶ下げてんねんで」 「とりあえず十万やったら四十錠やな。これでもだいぶ下げてんねんで」
「わかった」 「残りはいつにする?」 何とかして次は誰もいない時に来させてモノにしようと倫彦は思っていた。 「誰?どんな子?」 着替えて来た女が台所からやってきた。 「商談ん時は来んなって言うてるやろ」 「別にええやん」 女が髪をブラッシングしながら来ると玄関先の少女と目が合った。 「こんばんは先輩」 少女が口だけにこりと笑う。 「む、連…?」 女はかたん、とブラシを落とした。 「何やおまえら知り合いか」 驚愕の表情をする女に倫彦は怪訝な顔になり、ポケットのナイフに手をかけた。 「もしかしてヤバい奴なんか?」 そして倫彦はもう一度少女を見た。一方、女は突然何かを思い出したようにハッとした表情になる。 「い、いやや。あの事は言わへんから。殺さんといて。いやや!ウチまだ死にたない!助けて、お願いやから」 少女が薬の空き瓶をポケットから取り出し、にやあと笑う。 「習慣性が強力な抗殻精神剤。あかんなあ。こんな悪い薬売ってたら」 「なんやと」 連と呼ばれた少女はポニーテールを縛っていた赤い紐を解いた。そこからは何かの動物のような耳が現れ、スカートからはイエローオーカー(黄土色)のふさふさした毛に覆われた尻尾が垂れ下がった。 「…き、狐?」 倫彦は直感で思った事を口にした途端、女は楽しそうに嘲笑い、二人を指さした。 「ばいばい」 同時に決して外には漏れ聞こえる事は無いディーゼルハンマーの鎚音の様な、かん高い炸裂音が室内に鳴り響き、一対の鮮血が放射線状に飛び散った後、カーペットの上に降りそそいだ。 血痕がついたパソコン机の上のデジタル時計は七月一日午前二時七分を表示していた。 午後四時二分とテレビの上のビデオデッキの時計は表示されている。 みずきはソファに腰掛けながら憂鬱な表情でブラウン管を眺めていた。 『「お嬢さん、一人でふてくされてるなんて可愛くないですよ」 「違うもん!あたし、ふてくれさてなんかいないわ!」 「…どうだかね」 「誰も…、誰も私の気持ちなんか分かってくれないのよ!」 「悲劇のヒロイン気取りもたいがいになさったらどうです」 「ヒ、ヒドイわ。うわあああああん」 「お嬢さんっ!』 テレビドラマの主人公の少女がバースデーケーキを投げ捨てて泣きながら走り去って行く場面だった。 「つまんないドラマぁ」 みずきは手元のリモコンでチャンネルを変えた。 『「てえへんだ親分!」 「どうしたってんだ佐吉?」 「奴ら、まだ居すわっていやがりますぜ。まったく図々しい奴らだぜ」」 「まあ、落ちつけや佐吉。奴らも未来永劫、居着くって訳でもあるめえし」 「だってよぉ親分。おいら何だか悔しくて…」 「佐吉、一人でふてくされてるなんて情けねえぜ」 「違いやすよ親分、おいらふてくさてれてなんかいませんぜ」 「…どうだかな」 「誰も…、誰もおいらの気持ちなんか分かってくれねえんだ!」 「ガキみてえな事ぬかんすじゃねえ!」 「ヒ、ヒドイや。親分のバッキャローォォォ」 「お、おい佐吉ぃっ!」』 テレビ画面は時代劇の岡っ引きが十手を投げ捨てて泣きながら走り去っていく場面だった。 「つまんない時代劇ぃ」 そしてみずきはソファ越しに振り返ると、沙居と裕子と幹人とちひろはまだ遊びに興じていた。 (あの子達、いつまでいるのかな…?) 沙居と目があった。沙居がにこっと笑う。 ムッとしたみずきは再びしかめっつらでTVを見始めた。 それからみずきはもう一度振り返って今度は幹人の様子をちらりと窺った。 幹人はヘラヘラした顔をしながら裕子にレゴブロックを渡している。 …みずきはなんだかさっきより非常にムカついた。 ソファの上であぐらを組んであごに手をあてたみずきは煎餅を齧りながらヤケクソでTVを見た。 (あたし、ふてくされてなんかないもん!) そう心の中で叫ぶみずきにブラウン管の中でタバコに火をつけたスーツ姿のダンディな中年紳士が紫煙を燻らせながら言った。 『「…どうだかな」』 (以下次回) |