| 「朝霧さん程の人が気配を悟られるとは相手の子はよっぽど訓練された子って訳やねんね?」
「申し訳有りません。不覚を取りました。ですから尾行を一旦中止して、お聞きしました名前で住民登録を当たりました」 「基本に忠実な調査方法やわね」 「恐縮です。ただ…」 「ただ?」 「私も径間以外の間の者を見るのは始めてなので」 「そんなんはよろしわ。それでどないなんです?」 「はあ。近くの漢方薬局の子供という事までは」 沙居と朝霧の会話を聞いていた裕子は嬉しそうに立ち上がった。 「ではさっそく…」 「さっそく何ですか?」 端から見れば裕子の妹のような歳格好の沙居に見据えられ裕子はまた座り直した。 「…その、会って確かめてみればいいかと」 「まあ、それはそうとして、皆さん気づいてへんかもしれませんやろけど、確かにあの女の子らは奥間の者です。そやけどウチが問題にしてんのはもう一人のお人の事です」 「あの少年も奥間なのだろう?少々匂いは違ったが」 綾二郎がそう言った。 「いえ、お館様。あれは、あの感覚は間違いなく唯間様のもんですわ」 「唯間と言うと、上主様の…?本当か、沙居」 「はい、お館様。おそらく間違い無いかと」 そこで沙居以外の者の顔つきが変わった。真剣な、それでいて何やら嬉しそうな表情に。沙居は径間の人間のこの顔を見るのは何百年ぶりだろうかと思った。 少し考えて綾二郎が立ち上がってから言った。 「すまんがみんな席を外してくれ。儂と沙居だけにしてくれんか」 「は、はい。おじいさま」 「かしこまりました。さ、お嬢様」 裕子と朝霧が退室すると道家家のソファがある応接室には綾二郎と沙居の二人だけとなった。そこで綾二郎は改めて沙居を見つめた。沙居は、この万能自律人形は言わばこの道家家の家宝だ。その昔、遥か数百年前、主筋であり上主の唯間派から拝借と言う形で下げ渡されたものだと聞いていた。綾二郎自身も幼少の頃からこの沙居に育てられ言わば乳母のような存在だ。ただいつもいつも奇妙に感じるのは沙居の姿が十歳の少女の姿でしかも数十年前と全く同じ姿だと言うことだ。 そして今もその「家宝」が道家家の女中頭として家の中を歩き回っているのだ。 「坊っちゃん」 「その言い方はええかげんやめてくれへんやろか」 二人きりになる時、いつも沙居は七十年前と同じ呼び方で綾二郎をそう呼ぶ。 終戦直後、綾二郎が軍属として満州にいた頃、ソ連兵に取り囲まれた友軍を逃がすため単身、囮となって捕虜になった時に道家家から救出に来たのもこの沙居だった。 数十人のソ連兵を薙ぎ倒し戦闘機を奪って間宮海峡を越えて脱出した時の事は今では道家家の伝説になっている。その時も「坊っちゃんはいくつになっても世話の焼けるお人ですなあ」と脱力した声で言った事を綾二郎は昨日の事のように思い出せた。 「失礼しました。お館さま」 おそらくわざと言っているのだろう。綾二郎は今さらながらこの沙居を創った当時の唯間派の人間の底深さに畏怖を感じた。 「なんでそんな簡単に唯間様やとわかるんや?唯間、上主様の事は道家の先祖代々が繰り返し繰り返し探したのに今まで全く見つからんかったんは沙居も知ってるやろ」 「そら知ってます。ウチも上主様の捜索に参加した一人ですから」 「なんで今になって」 「おそらく結界が薄まったせいやと思います。ウチが考えますに当時の唯間の当主様は時限結界をお張りになられたんやと推察します。結界と言うよりも封印と言うた方が妥当かもしれませんけど」 「時限、と言うと時間的に限定された結界か」 結界にはいくつか種類があるが間の者が使う結界は外部の人間の思考、感情、情報を操作する事によって外部からの進入を阻むものだ。当然、道家の径間のこの屋敷にも力は弱いが同じ様なものが張り巡らされている。普通の人間ではこの屋敷に入りにくいような作用が生まれるのだ。 「結界でみつからんようにしとったんは分かる。でも何で時限式なんや? 今の時代に結界が解かれるように当時の上主様は設定されとったんか」 「それは…」 珍しく沙居の表情が曇った。 「あの頃の、唯間派の当主様、種名(シュナ)様のお心はウチにもよう分からへんのです」 唯間派の種名とは沙居を径間が借り受けた当時の唯間派の当主の名前だ。当然、それまでの沙居の主は種名だったのだ。 「ただ分かってんのは種名様は間の者の宗家、間使いとしてのご自分にお疲れなさってたと言う事です。最後にその事を聞かされたんは15世紀の終わり頃の今のインドネシアにあったある日本人町の港ですわ。奥間の娘に伝え聞いたんが最後です。 奥間の者に会うたんもその時が最後ですわ」 そう言えば。 沙居は当時のメモリーをしばらくぶりに記憶葉上にロードさせながら「あの頃」 の奥間の娘と先日、玄関先に来ていたあの姉の方の奥間の女の子がどことなく感じが似ていた事に気がついた。 堺商人達の船に乗って降り立った遠くシャムを望む南の地で出会った美しい奥間派の少女。奥間派独特のしなやかな体躯、南国の強烈な日差しでも白い肌の異国の衣装に身を包んだ少女。 …もしかしてあの子達はあの時の娘の子孫なのだろうか。 あの少し勝ち気で生意気だけど本当は寂しがり屋だったあの娘の。 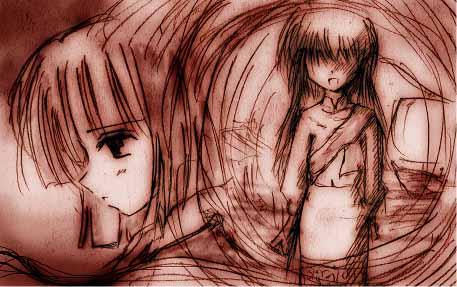
沙居がやや伏し目がちで佇んでいる時は過去の事を思い返している時だと綾二郎は経験から知っている。子供の頃、綾二郎は沙居が今のような表情をしている時、自分を取り残してどこか遠くに行ってしまうような寂しさをいつも感じたものだ。 いや、おそらく今もそうだ。径間の人間は皆そう思ってるだろう。何故なら径間の、道家家の人間は皆、沙居の事が大好きなのだから。 「何にせよ、あの異常に頭が切れた種名様の事ですから何かお考えがあっての事やと思います」 「…そうか。なあ、沙居」 「なんです?」 「儂も先祖伝来に伝えられたその上主様にもう一回ちゃんとお会いしたい。親父も爺さんもよう言うとった。道家の今の財力もそれからおまえも、みんな上主様に頂いたもので成り立ったもんやと。だからちゃんと探し出してお返しをせなあかんて。そうせんとご先祖様から怒られるってな。儂も、…俺もそうありたいと思っとる」 「そうですなあ。先代も先々代も道家のお館様はみんな、ええお人らでしたからなあ。あ、勿論、坊っちゃんも」 沙居はすっきりと微笑んだ。 子供だった頃の綾二郎をからかう時と同じく、 「あの頃」とも同じように。 |