| (こ、こわー) しかし。と、幹人は改めて昨晩の事を思い出して恐くなった。今だ涎を垂らしながら白目を向いている米谷を見るにつけ昨晩自分がこうなっていたのではないかと思うと戦慄を禁じ得なかった。汗一つかいていないみずきは全く何事も無かったかのように恐る恐る幹人に近づいてきた。 「大変なの・・・。ちひろが一人で勝手にどこかに行ったみたいなの。昨日の事はその・・・謝るから・・・だって男の子はああいう本を普通に読むって知らなかったから。だから・・・あの・・・その一緒に探して欲しいの!」 この子は大物なのかアホなのか幹人と連は呆然とした。今、さっきこの地域の幹人の年代の社会にとって衝撃的な事件が起きたのだ。だがみずきはまるで鼻をかんだハナ紙をクズカゴに放り投げた程度にしか思っていない節があった。 幹人と連は目を合わせた。起こった事態は迅速に処理する必要があった。 「わかった。一緒にちひろを探す。でもその前にやな・・・」 幹人と連は倒れている米谷に近寄ると足でげしげしと蹴りながら大声を上げた。 「うわーっ、こいつ小学生のしかも女の子に負けてやんの〜ハズカシィ〜!ハズカシィ〜ハズカシィ〜しかも一発もやりかえせんでやんの〜超カッコ悪〜。 言うたろ〜♪言うたろ〜♪みぃ〜んなに言い触らしたろ〜♪みなさ〜ん米谷はしょうっがっくせいの女にけんかで負けました〜。ええか〜、この事言い触らされたー無かったら二度と俺とこの子に近づくなよわかったか〜?あーん米谷ぃ〜」 我ながら情け無い事をしていると幹人は思ったがこのまま放置しておけば必ず米谷は報復を仕掛けてくるに決まっている。みずきと自身の安全のためにはまだ動けない間に米谷のプライドを再起不能(ズタボロ)に陥れておく必要があるのだ。一度ケンカに負けたという噂が立つことはこの年代特有の、特にこの地域の暴力的中高生人間関係社会に於ては存在的死を意味する。それは頂点に立っていた者ほど際だっていると言える。このように誰かに蹴落とされた人間の傷に即座に塩を塗り込むような行為はこの地域一帯に住んでいる少年達には保身の為の処世術として当然の行為として浸透していた。 「しかし、まだ若いのに姉さんめっちゃ強いなあ。グレイシー柔術か北斗神拳でも習ってるんですか?」 しばらく蹴り続けた後、気絶した米谷を電信柱傍のゴミ捨て場に投げ込んだ後、調子のいい連は既に年下のみずきを「姉さん」呼ばわりしていた。 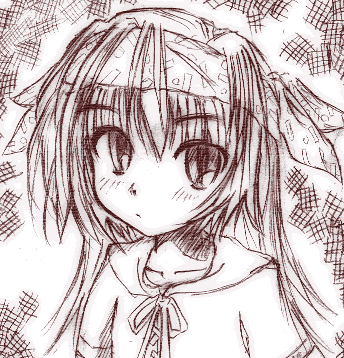 「おにーさん、この人だれ?」 「おにーさん、この人だれ?」
みずきは連を指さしてこわごわ幹人を見上げて尋ねた。 「え、ああ。連って言うて俺の友達」 「どーもー、むらじよしふみでえす」 「ふーん。あ、あの生方みずきって言います」 「生方、こ、こ、この姉さん、おまえの妹なんか?おまえ、こんな強い妹おったっけ?」 「朝言うたやんけ。再婚相手の連れ子」 「この姉さんが?」 連は改めてみずきを見た。頭にアクセントなのか水色のバンダナを巻いてキョトンとこちらを目を覗き込んでいる。よく見ればほんとに普通の小学生の女の子だ。 しかも可愛い。少々つり目だが。自分の妹もひいき目で見てそう思っているが、将来この子は美人になると連は確信した。そして幹人の方を見た。 「生方、これからは・・・」 「『アニキと呼ばせてくれ』なんか言うなよ」 「素晴らしい洞察力だね生方君。さすがは我が強敵(友)だ」 「あ、あのー、喋ってるとこ、悪いんだけどー」 腕を組んで無言でうなずきあっている二人を見てたまりかねてみずきが口を開いた。 「ちひろが・・・ちひろが・・・」 みずきは半泣きになりかけていた。 ああそうか。ちひろを探さなければならないのだった。幹人はようやく思い出した。あんなにすばしっこい子だからしてきっとその辺と言うその辺をかけずりまわっているに違いない。おそらく笑いながら。 「あの子、いっつも力いっぱい走り回るくせにものすごい方向音痴なの。前の家の時もあたしが何回も何回も溜め池からとかから家までの道教えても必ず反対方向に行っちゃうんだよ」 「あ、東京弁」 連が呟いた言葉を無視して幹人は考え込んだ。 「でも子供の足やからそんなに遠くには行かれへんやろし・・・」 と言ってから幹人はもう一度考え込んだ。子供と言ったがそれは世間一般の人間の子供の話の事だ。幹人には奥間の人間の幼児の運動能力のスペックなど知る由もなかったが、今朝のフライングエルボードロップの技の凄まじさから推し量るに・・・。 そこで幹人は考えるのを止めた。無意味だからだ。 「探すにもあたし、まだこの町の事よくわかんないし」 みずきは不安そうに下を見た。もしかしたらこの子もちひろ程では無いにしても方向音痴と言うことでは似たりよったりなのかもしれない。幹人は何となくそう思った。あんなに強いのに、と。それからもう一度ゴミ捨て場でのびている米谷を見やった。 「よし、生方、ここは手分けして探そう。ようするに一人で歩いてる小さい女の子を探したらええんやろ?」 「まあそやな」 「おれは姉さんと向こうを探す。おまえは駅の方を頼むわ。さあ、行きましょうかみずき姉さん」 「えっ?えっー?」 連は目を白黒させているみずきの手を取って商店街がある方向に歩いて行こうとした。 「待たんかい。なんでおまえがこの子と行かなあかんねん」 「何か問題でも?」 幹人はこいつは小学生にまで手え出すんかいな?と半分呆れたが、とにかく奥間の正体がバレるのはマズいと言う理由でみずきを取られるのは嫌だという本心を隠して自分を納得させた。それから連に向かってとりあえず何か言おうとした時、連はにやりと笑って呟いた。 「やだぁ幹人お兄ちゃん、ひょっとして今ジェラ(嫉妬)ったね?」 「あのなあ」 「ジェラったって何?」 みずきはフェリーの中の売店でちひろと一緒に食べたアイスクリームの銘柄が頭に浮かんで尋ねた。(←それはイタリアンジェラード) 「今度ゆっくり教えたるわ」 こんな事をしている場合では無かった。 「わかったわかった。道すがら俺一人で探すわ。なんか事情もありそうやしな。 もしそれらしい子見つけたらおまえんとこの店に電話したらええな?」 「悪いな連」 「ほんなら、姉さん、さっきは助けてくれてありがとうな。ほんなら!」 ・・・手を挙げて去っていく連と別れた幹人とみずきは猫屋敷の外周を歩き始めた。 「どうしようどうしよう、あたしが目を離したばっかりに・・・」 すっかり気を落としてるみずきを見て幹人は可哀想に思えてきた。 「しかしどこ行ったんやろ・・・?」 どこから探そうかと考えあぐねていたその時、 ふと、幹人の心に風が吹き込んできた。もちろん『それ』は風などではなく、何かの波紋のようなものだった。事実、辺りは全くの無風なのだから。そして『風』はお日様を浴びた子猫のようなふんわりとした感触でもあった。 (な、何やこれ?) それは第六感と言ってもいい幹人にとって生まれて初めての感覚だった。 「どーしたのー?」 みずきは急に立ち止まった幹人を振り返った。 「ちひろは・・・こっちや!」 幹人は元来た方向に向かって走り始めた。 |