| 「ふう、やっと片づいて来た」 みずきは午前中を費やして部屋の掃除と片づけをしていた。みずきとちひろの二人にあてがわれた部屋は三階建ての生方家の中二階に位置する南向きの角部屋だ。みずきがまずこの家に来て驚いたのは玄関が三階にあると言うことだった。 つまり一階は畑と田んぼに囲まれて事実上通行不可能、家自体が小さな切り立った崖にもたれかかるように建っているのだ。その崖の上の道路沿いに三階があり、ちょうど、道路から見ると一階平屋のように見えると言うあんばいなのだ。 (ヘンな家ー) と、この家を見てみずきは思った。だがしかし、繁に中二階の部屋を見せてもらうと家の外観の事などどうでもいいと思った。つまりは部屋が気に入ったのだ。 屋根裏っぽいその部屋はみずきが憧れてた童話の「小公女」の主人公の部屋に何となくイメージが似ていたからだ。 (プレゼントを持って来てくれるインドの人がいないのは仕方無いとしても、ここはセーラの部屋より暗くも無いし狭くもないしちょうどいいや) 元は事務室用だったので古い木製の机とか椅子とかが揃っていた。なんかこう、わくわくするものがあった。みずきはダンボール箱から自分の数少ない持ち物の本や思い出の人形なんかを取り出した。そして本を取り出してふと思い出した。 (あ、そう言えばあの人に本貸してもらうつもりだったのにあの事があって結局借りられずじまいだったな・・・) 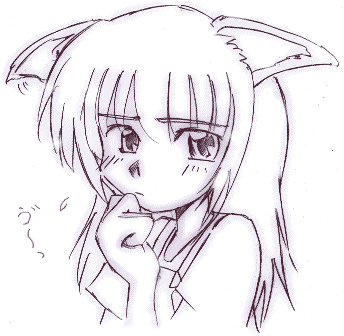 どうしようかな。今さらもう一回貸してとも言いにくいし。でもあの本はどうしても読んでみたいし。 どうしようかな。今さらもう一回貸してとも言いにくいし。でもあの本はどうしても読んでみたいし。
困った困った。 分校では年上の男の子がたまたまいなかった。皆、年下か年上の女の子ばかりだったので実際あの年代の男の子とは接した事が無かったのだ。 (なんか超えっちな本持ってるし、こわいし、やだなあ) 「おかーさーん」 みずきは階下に向かって母親を呼んでみた。 返事なし。 おそらく、隣の店の方に行っているのだろう。母の友美さんも今日からは生方(うぶかた)漢方薬店の店員というか助手の一人だ。店番とか倉庫の整理や掃除なんかをすると昨日言ってた事をみずきは思い出した。 母屋の隣に建っている『生方漢方薬店四田本店』は事実上、「地下」三階、「地上」二階の五階建てで、神戸と大阪と姫路に支店がある中規模の「そこそこ」名の知れた漢方薬店だ。この店の売りは他の漢方薬店とは一線を画す独自調合の煎じ薬であり、何件かは特許を取っている製法もある。みずきは耳を隠すために水色のスカーフがわりのバンダナを頭に巻いて隣の店まで駆けて言った。 「おかーさーん!」 木製の戸をがらりと開くと繁はレジがあるカウンターの奥のパソコンでソリティアをしていた。暇そうだった。 「おとーさん、おかーさんは?」 「奥の棚で色々覚えてもらってるとこや」 「奥?」 みずきは店の奥にに遥かに広がるやはり木製の棚の列を覗いて見た。そこには色とりどりの薬の原料や生薬の粉末が円筒のガラスのビンに入っていて整然と並んでいた。 「わー、すごーい。ね、おとーさん、中入ってもいい?」 「ええけど、ビンには触らんといてな」 「うん、わかった」 みずきはおっかなびっくりの様相で薬品棚の奥へと歩いて行った。みずきにとって薄暗いことはさして問題では無かったがやはり、ひんやりした気温と雰囲気がちょっと怖かった。 「おかーさーん、どこー?」 みずきの声が薬品庫の奥へと吸い込まれていく。 「・・・で、この五十二番のビンが鬱金ね。あと、葛根湯(かっこんとう)とか売れ筋の物はまとめてこの保湿庫に入れてあるから、ほら、これみたいに最近はアガリスク茸とかブラジル産の物が多いの。それからお茶とかも主力商品の一つね」 「なるほど・・・いっぱいあるんですねえ」 「でも友美お姉さん物覚えが早いわぁ」 「私の田舎でも母がこれと同じような物を作ってましたから」 「ああ、そやったね。元は言うたら薬の製法は同系やもんね」 奥から友美さんともう一人、女の人の声がしてきた。その女の人がキョロキョロしているみずきを見つけて声をかけて来た。 「あら、あなたがみずきちゃんやね」 少し小柄だが白衣を着てメガネをかけていて、ポニーテールに黄色のリボンをつけている。愛想がよさそうな女の人だった。歳は友美さんとそう変わらないか少し下くらいだった。 (誰だろう・・・?) みずきが不思議そうに見上げると今度はやはりスカーフを頭に巻いた友美さんが書きかけのメモから顔を上げみずきを見つけた。 「あら、どうしたの?みずき。あ、この人はお父さん、繁さんの妹さんの岬さんよ」 「は、はじめまして生方みずきです」 みずきはこう言う所は躾(しつ)けられているのでとりあえずきちんと挨拶した。「んー、ええ挨拶やわね。はじめましてみずきちゃん、あなたのお父さんの妹の生方岬って言うの。よろしくね。みずきちゃんのお母さん覚えが早くて何か期待できる新人って感じやわ」 そう言って幹人の叔母にあたる岬はにっこり笑った。 「は、母をよろしくお願いします・・・」 そうみずきが言った途端、岬は爆笑した。 「ええわ。なかなかええわ、この子。気に入ったわ。こっちこそよろしくねみずきちゃん。じゃ、友美さんお姉さん、そろそろお茶にしましょか?」 「そうですね」 人当たりの良さそうな岬の笑顔にみずきはほっと安心した。しかし、岬のその笑顔にほんの少しの僅かな陰りが見受けられた事にみずきは気づかなかった。そして程なくして幹人が同じような表情をするようになった事にみずきが気づくのはそのずっと後の事だった。 「幹がエロ本を?あははー、おかしー。あの子もそんな歳になったんや」 薬品庫の真ん中の事務机で4本の昼光色の40W直管蛍光灯に照らされながらみずき、友美さん、岬の三人はビスケットをつまみながらお茶を飲んでいた。 「だってだって、すっごくえっちな本だったもん」 友美さんはため息をついた。 「それで今朝、幹人さんのおでこに引っ掻き傷があったのね」 「言わなくてごめんなさい」 「気にせんでええで、みずきちゃん。そら幹が悪いわ。そろそろ年ごろの女の子にそないなえげつない本見させるんやから」 (ホ、ホントはあたしが勝手に見ちゃったんだけど・・・) 「でもまあ、みずきちゃん、幹の事、許したってえな。年ごろの男の子はみんなそんな本読みたがるもんなんやから」 「え、そ、そうなの?」 「そうそう、ウチの兄さんも独身時代に必死に隠しとったけど。ウチはみんな把握しとったわウチが中学ン時やけど」 岬はフフンと鼻を鳴らした。 「そういえば、みずき」 友美さんがあっと言うように声をあげた。 「ちひろはどうしたの?」 みずきはお茶をごっくんと飲み下してからがたんと音を立てて立ち上がった。 その事でここに来たのを忘れていたのだ。 「あーっ!」 |