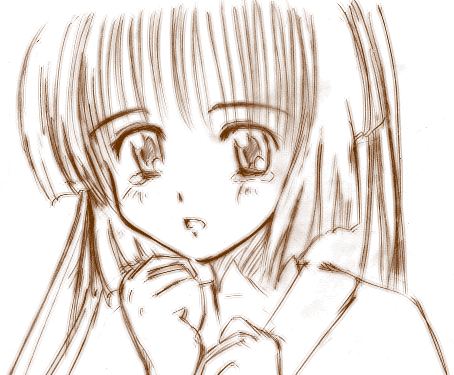| 道家裕子(ドウケユウコ)が登場する。
彼女は幹人や周りの住民が秘かに猫屋敷と呼称する屋敷の12歳になる一人娘だ。 道家家はこの街有数の資産家で最近、本来別荘であるこの屋敷を本宅と定めて越して来た。道家家の人間には他人には絶対知られてはならない血の秘密がある。 かつて道家の人間は径間(ケイマ)の者と呼ばれていた。卓越した反射神経と運動能力と知性を兼ね備え戦国時代に於ては闇の傭兵として暗躍していた。しかし決して表舞台には姿を現す事は無かった。それはその径間の者の特性が犬のそれであったからだ。遺伝子交配的人工改良品種。人狼という程のものでは無いがそれに近いものがある。第一、狼では主がコントロールできない。犬そのものに変身する訳では無いが状況に応じて、身体の一部を牙、爪、耳、尾などに変化させ、武器無しで自在に戦う事ができるのだ。だがある戦いの後、径間の者達は主と逸れてしまい取り残されてしまった。根が犬なので主がいなければその力を発揮させる事ができない。その頃には戦が必要のない世の中になっていたので逆にその能力は迫害の対象になるのは目に見えていた。一族は径間の名と能力を隠し、いつか本当の主に再会できる事を夢見て細々と生き延びてきたのだ。 しかし同族婚が多かったせいか現在ではその血の力は若干薄まって来ていた。そんな中で裕子は生まれつき、径間としての能力は高かったが病弱でもあった。一度も学校に通った事が無い彼女の世界は度々いれかわる家庭教師達の話や窓から見える景色とこの最近越してきた屋敷の外界から隔絶されているような肌色の塀とその上に広がる空だけだった。 そんな裕子を見兼ねて事業を息子夫婦に引き継ぎ隠居生活を送っている祖父が不憫に思い、近所の猫たちを餌付けしてせめてもの慰めとしていた。それが猫屋敷の真実だった。 屋敷の中庭(パティオ)で日光浴を日課にする裕子は塀の上を優雅に歩く猫を見るのが好きだった。 彼女はいつものように雨上がりの雲の切れ間から見える青空を見ていた。雲は形を変えながら西から東へと大急ぎで走り抜けていく。風がやや強いようだ。ふと目を落とすといつもの塀の上をピョートル大帝が何かに追われるように走り抜けていった。ピョートル大帝とは裕子がその茶色の猫につけた名だ。 「ねこさーん、まってー」 そこにトコトコと女の子が歩いてきた。もちろん塀の上を。 地上数mの塀の上を小さな人間の女の子が歩いている。あまり信じられない光景だった。その内、女の子はスキップを始めた。 「あぶない!」 裕子はロッキングチェアから立ち上がって声を上げた。長い黒い髪がぱらりとガウンの上に広がり落ちる。 その距離、10mはあったが裕子の能力をもってすれば1秒弱で跳躍できる距離だ。その代償は女の子に自分の正体を知られてしまう事、急激な運動による寄せ返しで2、3日は寝込んでしまう事、大好きなおじい様に叱られる事。様々な思惑が裕子の頭の中を駆け巡る。どうしよう?どうすればいいんだろう?的確に、例えそれが間違った事だとしても行動を指示してくれる人が欲しかった。裕子はそれが自分の優柔不断な性格のせいだと思っていたが実は道家家の人間全体に言える事なのを彼女は知らない。 「ちーちゃんの事、よんだ?」 ちひろは声がした方向にバックステップして振り返った。その時、ちひろの足が滑った。 「キャーッ!」 悲鳴をあげたのは裕子だった。転がり落ちていく女の子にただ立ちすくんでいた。我に返った裕子はスリッパのまま泣きながら走った。 どうしようどうしよう、私のせいだわ。私が自分の事ばっかり心配して動けなかったから、いいえそれ以前に私が声なんかかけなかったからこんな事には。 裕子は病気ばかりして迷惑ばかりかけている自分が嫌いだった。 かわり私が死ねばよかったのに。 彼女は以前、手首を切ろうと自殺を図った事があった。だができなかった。裕子は知らないが径間の者は潜在的に自殺ができないような精神構造になっているのだ。裕子はそれが自分が弱いからだと思い込んでいた。もっと強くなれればと。 「しっぱい、しっぱい」 茂みからちひろは頭を起こした。ちひろは発達した小脳と三半規管によって何も考えないで落下しながら空中で前転をして無傷で着地していた。 「大丈夫?ケガしてない?」 そこに茂みをかき分けてゆったりとしたローブ姿の裕子が現れた。 ちひろはほけーとしながら顔を上げた。綺麗なお姉さんだと思った。みずきには悪いがおねーちゃんよりも美人だと思った。 裕子の指がちひろに触れたとたん、ちひろの髪が逆立ちビクッとした後、後方に 後ずさった。 犬! 本能が怖いという感情を刺激した。去年、奥間の里に野生化した土佐犬が迷い込んできた。さんざん追いかけられて泣きじゃくりながら木に逃げ登った事を思い出した。その時はみずきが駆けつけて犬を一撃で気絶させてくれて事なきをえた。その恐怖がまざまざと思い出されたのだ。 (このおねーちゃん い ぬ だーっ!) 女の子に触れた途端、撥付けられて怖がられ後ずられた事に裕子は深く傷ついた。 何かとてつもない罪悪感に充たされて裕子は悲しくなった。 「こわいーこわいーいぬこわいー!」 ちひろは泣き始めた。 「いぬきらいー、いぬこわいー、いぬいやー、おかーさーんおとーさーんおねーちゃーん、うわーん」 会って24時間も経っていない幹人の名前が入っていないのは仕方が無かったが、とにかくちひろはこの世の終わりのごとく全身全霊をもって泣き叫んだ。 裕子は犬と呼ばれた事とこうも自分を完全否定された事がかつて無かったので更に深く傷ついた。 「ごめんなさいごめんなさい」 裕子の目から涙がぽろぽろと溢れだした。小さな女の子に怖がられる事の切なさで立っていられなかった。裕子は世界全体に謝っていた。自分の存在を含めて。
すると、ピョートル大帝を含めた猫たち十数匹がが何事かと言う風に集まって来た。ナーゴナーゴと裕子とちひろを見上げて鳴き始めた。 |