| 「生方、なんやその引っ掻き傷は?」 始業までの間、教室でボーっとしている幹人に親友なのか悪友なのかよく本人にも解らない連義史(ムカジヨシフミ)が話しかけてきた。 「いや、なかなか激しい女でな・・・」 激しい女、確かに嘘では無い。 「嘘つけ、どうせ猫にでもやられたんやろ?」 猫、それもあながち真実を示していなくもない。 「ま、そんなとこやねんけど・・・」 「朝っぱらからおまえにしてはおもろいギャグやったわ」 幹人は事情を説明しても仕方がないのでとりあえず肯定しておく事にした。 「この本返しとくわ」 幹人は傷の元凶となった写真集を連に渡した。 「なかなか倒錯的でよかったやろ?」 「ちょっと倒錯的すぎたけどな・・・それより実は俺の父親が再婚しててなあ」 「へー、あの北杜夫みたいなおやっさんが?」 連は時々、幹人の家に遊びに来ていて父親とは顔なじみだ。幹人にはよくわからないが連はしきりに幹人の父親、繁が作家の北杜夫に似ていると言って聞かなかった。 「それで北杜夫パパの相手はどんな女やねん?」 「うん、えーと30歳くらいのわりかし美人の人やったわ」 「なにぃー?それってメッチャ年下やんけ。確か北杜夫パパは40過ぎやろ?」 「そうやけど」 「若くて美人の義理のお母さん!」 「それがどないしてん?」 連はにやりと笑うとカバンからごそごそと文庫本を取り出した。 「おお、それはおふらんす文庫」 その筋のポルノ小説だった。ずばりタイトルは『義母の匂い』 連はニヤニヤと笑う。 「おまえ、何が言いたいねん?」 「生方くんのえっちいいいい」 連が大声を上げたので教室の連中が何事かとこっちを見た。 「ええのお、美人の若いお母さん、その内にご挨拶に伺うわ」 「来んといてください」 「つれないねえ生方君」 「連れ子もおんねん」 「男?女?」 「妹やな」 「ほお。妹か」 「連ンとこも妹おったよな?」 「陽子の事か?おまえにはやらんぞ」 「おまえをお義兄さんとは死んでも呼びたぁないわい。でも妹ってようわからんけど、どんな感じなん?」 「そらちょっとむつかしい質問やな。ウチんとこの妹はちょっと変わってるからな」 幹人は一回だけ連の妹を見かけた事がある。小学生だが背丈は幹人とそんなに変わらない長身の少女だ。あの調子だとすぐ幹人の背より高くなりそうだ。無口で何を考えているか判らないとこがあるそんな雰囲気を持っていた。 「会話が無いとか?」 「いや、日常会話はしてる。時々小学校フケてるみたいやけど」 「小学生で既にサボってるんかい、不良か?おまえんとこの妹は」 「なんか一時期問題になったけど成績はええねんウチの陽子は。ウチの親も放任のとこあるからな」 「フケて何してんの?援交でもしてんのか?」 「そやったら面白いけどな。もしそうやったら俺、妹使って美人局するわ。 でも、なんか外で絵描いてるみたいやな」 一匹狼。幹人の頭にそんな言葉が浮かんだ。この連にしてもアウトローなところがある。この男は中学生のくせにタバコも吸うし隣の女子高との交友関係も派手らしい。かと言って不良ではない。だいたいこの中学は受験に合格しなければ入学できない。頭が悪ければ入れないのだ。そう言う意味合いにおいて、優等生でもなければ不良でも無く、かと言って幹人が位置する「中間層」ですら無い。必然的に連には友達が少ない。何故か幹人とだけは気が合うようだ。周りから見れば「不良っぽい」連に付き従ってる「かわいそうないじめられっ子」の幹人と見られている節もあるが実は立場的には対等につきあっている。どうも妹もその線にあるようだ。 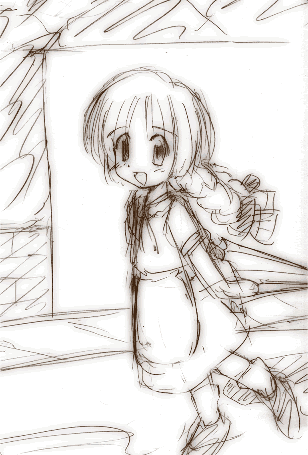 「にゃんにゃんにゃん♪」 雨がやんだのでちひろは友美さんの目を盗んで外を散歩していた。母親からはきつく言われているのでとりあえず耳はつけ油で倒している。 ちひろにとって見るもの聞くもの嗅ぐもの、何から何まで生まれて初めての体験だった。雨で濡れたアスファルト、電柱、水たまり、まっすぐな道路にたくさんの人達。 世界はこんなにも輝いて大きく広がっていたのか。 ちひろは大きな目をさらに丸くして両手を広げてたたたと駆けながら雨上がりの空気の匂いを嗅ぎ、風が髪を体も心も清々しく吹き抜ける事に大喜びだった。 「うにゃ?」 ちひろがふと足を止めると茶色の毛並みの猫が目の前を悠然と通りすぎていく所だった。実はちひろは本物の猫を見るのは始めてだった。奥間の里にはいなかったからだ。だが絵本やテレビでそれがどんなものなのか知っている。 「あー、ねこー!」 おいかけよう。おもしろそうだから。 自然に楽しくなった。一人でも楽しいことがあれば笑う。ちひろはそういう子だった。それはひっそりと暮らしていて姉しか遊び相手がいなかったためのちひろなりの心の自衛策でもあった。 猫は追いかけられている事を感じてひらりとある屋敷の塀によじ登った。ここに上ればたいていの犬、人間の子供からの追跡を躱せるからだ。猫はちひろを見ろして勝ち誇ったようにナーオと鳴いた。 ちひろは立ち止まってちひろの目からそびえ立つように立ちはだかる塀とその隙間から見える屋敷を垣間見た。 「わー、おっきなお家ー」 塀の上を見上げるとさっきの猫が地上2m半の所でナーオと鳴いている。 ちひろは高い所が好きだった。 「待っててね今すぐのぼるね」 ちひろはそう猫に宣言してから両手を塀にかけて勢い良く一気に塀から更に3m上空までジャンプすると空中でくるくると2回後転して両足で綺麗に塀の上に着地した。奥間の者の遺伝子的に強化された運動神経ではこの程度の事はちひろには容易にできる事なのだ。 それを目の当たりした猫は怖くなって逃げ出して行った。 「ねこさーん、まってー」 ちひろは20cmたらずの幅の塀の上を全力疾走して猫を追っかけ始めた。 |