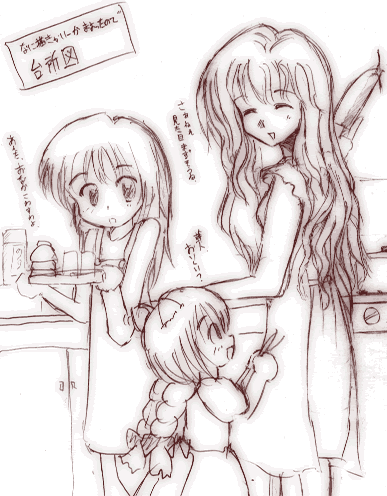 30分程して夕食の準備のいい匂いが台所から漂って来た。幹人は何故、先週の日曜日に父親が通常の3倍の食料を冷蔵庫に詰め込んでいたのかその理由がようやく理解できた。家族が2.5倍に増えるからだ。 30分程して夕食の準備のいい匂いが台所から漂って来た。幹人は何故、先週の日曜日に父親が通常の3倍の食料を冷蔵庫に詰め込んでいたのかその理由がようやく理解できた。家族が2.5倍に増えるからだ。
「今日はまだ立て込んでたから簡単なものしかできなかったけど幹人君の口に合うかしら?」
今日の夕食はサバの焼き魚に肉じゃがとみそ汁とオーソドックスなものだったが幹人にはとても新鮮だった。だいたい幹人にとって母親の記憶は2歳の時に途切れている。3年前に会ったがあまり実感というものがわかなかった。新しい母親。義母という事になる。普通ドラマとかだと反発したりするのだろうが事、若くて美人(猫耳だが)のこの友美さんという女の人には不思議と好感が持てた。母親という
よりは歳の離れた姉という錯覚すら覚えた。しかしながら素直にそれを表現できる程、幹人は器用では無かった。自分でもそれが分かってるだけに何だか歯がゆい。
「どうかしら?」
少し探るような上目使いで友美さんは幹人を窺った。
「あ、…はい。美味しいです…」
もっとましな事、例えば「いやー、目茶目茶美味いッス感動的ッス」くらい、ホントのところは言いたかったのだがなんだか妙に恥ずかしくてその程度の事しか幹人には言えなかった。
「当然よ。だって、おかーさんが作ったごはんだもん」
みずきはお椀を持ったまま、すまして言った。
「みずきも手伝ってくれたもんね」
友美さんは微笑みながら娘を見た。
「ちーちゃんもっ!」
「そうね。ちーちゃんもちゃんと手伝ってくれたもんね」
「うん!」
嬉しそうにちひろが笑う。身体全身を揺さぶって喜びを表現していたりする。仲の良い母娘だな、と幹人は見ていてなんだか羨ましくなってきた。
「やっぱり女の人が居ると潤いがあんなあ」
と父親の繁はコップにつがれたビールを飲みながらどこかで聞いたようなセリフを口にした。しかし何で5年もこの俺に再婚した事を黙ってたんやろ?と幹人は疑問に思う。まあ、再婚して連れ子をいきなり連れてきて(内一人は自分の実の妹)息子である自分の了承も無く強引に同居する事はまあいい。今さらこの父親の性格を云々する事はもはや諦めている。世間一般ではきっとよくある事なんだろう。もっと…何か根本的な事が欠落しているような・・・・。幹人は自動的(オートマティック)にごはんをかき込みながら六つの、三人の女の三対の猫の耳を見るにつけ既に違和感が無くなっている自分に驚いていた。
そうなのだ。こいつらは世間一般で言う異形の者なのだ。見た目、美人の奥さんにかわいい姉妹(姉の性格は別として)。実は頭の上についてる耳はアクセサリーでえええすとか言っても通じそうだ。尻尾は?尻尾はどうなっているんだろう?あるのかな?幹人の脳裏に巨大な氷塊がごぼりと浮かび上がるかのように大きな疑問がわき起こって来た。自分はこいつらの事はまだ何も知らない、というか知らされていない。だいたいこの親父が10も歳が離れたこんな美人を嫁さんにできたのも大きな疑問だ。不安だ。幹人は先行きがとても不安だった。
「どーしたの難しい顔しちゃって?」
みずきが怪訝な顔で幹人の顔を覗き込んだ。
「いや、まだ状況が理解できてないから」
「私は理解してるもん」
みずきはえへんと胸を張った。
「それにしても四国から来たのにあんまり訛ってへんな。東京の人みたいやな」
幹人は素朴な疑問を口にすると父親が答えた。
「この子の住んでた里は他に人がおらんかったからな。みずきは俺が買うたったTVばっかり見てたから何か知らん内に標準語になってもうたみたいやな」
「あたし、初めてフェリーに乗った時びくりしちゃった。だって廻りの人みんな漫才みたいな喋り方するんだもん。おとーさんだけかと思ってたから。ね、おかーさんもそう思ったでしょ?」
「そうねえ」
友美さんがそう言うとちひろも何か言いたいらしく
「はしがねー、はしがあったの!」
と叫んだ。
「瀬戸大橋と明石大橋の事でしょ、ちひろ」
みずきが補足してあげるとちひろはしきりに「うん、うん」と頷いた。
「ああー、でもここ前の所と違ってTVのチャンネルいっぱいあってあたし嬉しいよ。ね、おかーさん、後でTV見ていい?」
「ちゃんと片づけてからね」
「はあい」
「そや、幹人、明日土曜やから昼からこの子ら町、案内したれや」
「え?」
「ええー?」
父親、繁の言った事に幹人とみずきはほぼ同時に反応した。
「あたし別にこの人に案内して貰わなくたっていーもん」
「この人」呼ばわりされた幹人はさすがにムカつき始めたその瞬間、
「みずきっ!」
友美さんの一喝する声が台所をビリビリと走り抜けた。みずきの体躯がビクッと震えた。ついでに幹人もたじろいだ。それほどの威圧感だった。
「幹人さんはもう、あなたのお兄さんなのよ。それをこの人って何ですか。私達はお父さんにここに住まわせて頂くのよ。幹人さんは優しい人だから許して貰えるかもしれないけれど、目上の人にそんな言い方をするのはお母さん許しませんよ」
普段が優しそうな美人だけに怒ると物凄く迫力があった。みずきは箸を皿の上に置いて項垂れてしまっていた。
「ご、ごめんなさい・・・・」
ちひろだけが何喰わぬ顔でサバの骨をはぐはぐと齧っていた。
「お母さんに謝ってもしょうがないでしょう。ちゃんと幹人さんに謝るのよ」
ちひろはちら、と幹人の方に目を向けると「…ごめんなさい」と蚊の鳴くような声で呟いた。
「『ごめんなさいお兄さん』でしょう?」
「ご、ごめんなさい・・・・お兄さん」
「ごめんなさいね幹人さん」
申し訳なさそうに言う友美さんに繁は「まあ俺もみずきにお父さんって呼んでもらうのにだいぶ時間かかったもんなあ」とにやりとみずきに向かって笑った。顔を真っ赤にして繁からの目線を逸らしているみずきを幹人は何だか気の毒になってきた。
「ま、その別に気にしてませんから」
できるだけ穏やかな口調で言った幹人をみずきはもう一度、ちらりと見てきた。
「ええ、でもちゃんとしておかないと。みずき、もう二度とそんな事言っちゃ駄目よ。分かったわね?」
「はい」
それでようやくこの場が収まった。幹人にとってそれは生まれて初めての家族2人以上の団らんでもあり、山あり谷ありの夕食でもあった。
|